カタログギフトはどこで買う?購入できる場所から選び方まで解説
2025年11月3日
様々なお祝いやお返しに人気のカタログギフトですが、「どこで買えるのか?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
カタログギフトが買える場所は店舗やネットショップなど様々です。この記事では、購入場所ごとのメリット、デメリットをそれぞれお伝えしていきます。
また、カタログギフトの選び方、活用できるシーンやカタログギフトを贈る際の注意点まで解説しますので参考にしてください。
また、ネットショップでもカタログギフトの購入が可能です。ネットショップには、百貨店やギフト専門店のショップもあり、店舗にはないカタログギフトをチェックできます。ネットショップのみで販売しているお店ではショップ独自のカタログギフトが用意されています。
様々な購入場所がありますが、カタログギフトを購入するタイミングや贈る相手によって買う場所を検討してみてください。

インターネットでの購入が不安な方は参考にしてみてください。
目上の方や高齢の方へ贈る場合、有名百貨店のカタログギフトを贈ることで安心感があるでしょう。また、百貨店ごとにオリジナルのカタログギフトを展開していることもあるので、選択の幅が広がります。
普段の買い物でも活用している大型ショッピングセンターであれば、気軽に立ち寄れますし、買い物に行くタイミングでカタログギフトを買いに行けます。
大型ショッピングセンターは店舗展開も多く、違う店舗を比べることでカタログギフトの選択肢も増えるでしょう。
カタログギフトを初めて購入する場合であれば特に、ギフト専門店ならではの知識を持ったスタッフに聞きながら選べるのでおすすめです。
ギフト専門店の店舗数はあまり多くないため、行ける範囲が限られるかもしれません。
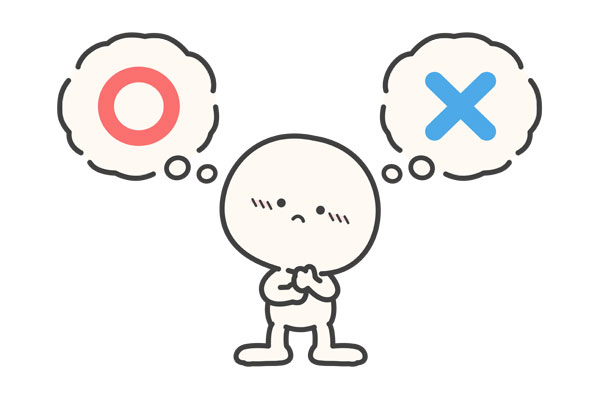
ここでは、カタログギフトを店舗で買う場合とネットで買う場合のそれぞれのメリット、デメリットを解説します。
実際に贈るカタログギフトの紙質や重さ、大きさ、高級感があるのかカジュアルな感じなのかなどを確認することで「持ち運びしやすく邪魔にはならないな」「意外と重いな」「もっと高級感が欲しいな」と気付くことができて、より相手に合ったカタログギフトを選べます。
また、カタログギフトを贈るシーンごとのマナーや、分からないこともその場で店舗スタッフに尋ねられるため、安心してスムーズにカタログギフトを選べます。
店舗ではカタログギフトの現物が見られますが、取り扱っている全てのカタログギフトが展示されているとは限りません。そのため、店舗にあるカタログギフトの中から選ぶことになります。
また、店舗で買うと、配送伝票の記入が手書きであることがほとんどで、贈る数が多い場合は手間がかかります。手渡ししたい相手のためにカタログギフトを購入して、その場で持ち帰りができないこともあるので注意してください。
お中元やお歳暮の時期は、贈り物を買いにくる人が多いため、待ち時間が長くなることも考えられます。時間に余裕を持って店舗へ行くようにしましょう。
ネットでは取り扱っているカタログギフト全てを確認できるので、様々な種類を比べて、より相手に合ったものを選べます。
多くのネットショップではデジタルカタログを使用して、画面上でカタログの中身が見られるようになっているため、自宅にいながらゆっくりと吟味できることもおすすめポイントです。
また、ネットで買う場合、送料無料やクーポンなどのお得なサービスが用意されているため、コストを抑えてリーズナブルにカタログギフトを購入できます。
さらに、カタログギフトの現物を贈るのではなく、オンライン上で贈れる商品もあるため気軽に贈ることも可能です。相手の住所がわからなくても贈れるショップもあります。
カタログギフトの実物を確認できないと不安な人は、ネットでの購入は避けたほうがいいでしょう。
また、疑問点を質問してもすぐに回答をもらえなかったり、スタッフの贈答マナーが不足していたりすることもあります。ネットショップのアフターフォローがどのようになっているかも確認が必要です。
まれに、贈り物にネットショップを利用することをよく思わない人もいるので、百貨店などのネットショップを利用するなど配慮しましょう。

カタログギフトを活用できるシーンはいろいろありますが、ここでは、香典返し、結婚祝い、出産祝い、新築祝い、様々な内祝いでカタログギフトを贈る場合について解説します。
相手に合わせたものを選ぶのが難しい場合も、カタログギフトであれば予算に合わせて選べますし、贈った相手に好きな品物を選んでもらえるので、おすすめです。
香典返しには細かなマナーや、しきたりが残っており、香典返しを贈る時期は、宗教や宗派によって変わります。仏式では四十九日の法要のあと1ヶ月の間に贈るのが基本とされています。
故人を思い、祈っていただいた方たちに失礼がないことが一番です。
カタログギフトであれば、新しい生活をスタートする2人が本当に望むものを選んでもらえます。また、2人で好きなものを選ぶ楽しい時間もプレゼントできるでしょう。
結婚祝いを渡すタイミングは、挙式がある場合は式の2ヶ月前から1週間前くらいの間が望ましく、挙式当日に渡すのはマナー違反とされています。
挙式がない場合は、結婚の報告を受けてから1ヶ月以内くらいに贈るようにしましょう。
贈られた人が好きなものを選べるカタログギフトは、初めての出産の人でも兄弟姉妹がいる人へのお祝いでも、本当に必要なもの選んでもらえるおすすめの贈り物です。
出産祝いを贈るタイミングは、生後7日から1ヶ月くらいの間とされていましたが、近年、産後1週間ほど入院するように変わってきたので、産後2週間から3週間に贈るのがベストです。
新築の家には建てた人の好みやこだわりが詰まっています。おしゃれなセレクトショップ監修のカタログギフトなど、新しいお家にあったインテリアや雑貨を選んでもらえる贈り物としておすすめです。
新築祝いに贈るにはタブーとされているものがあります。それは、「火事を思わせるもの」壁掛け時計のように「壁に穴を開ける必要があるもの」です。
カタログギフトは相手に好みのものを選んでもらうので、あまり心配はありませんが、赤い表紙のものは避けるのが無難です。
内祝いを贈る時には、贈るシーンごとにマナーがあり、地域によっても変わります。カタログギフトであればそれぞれのシーンに合わせて選べますし、贈るシーンに特化したカタログギフトも用意されています。
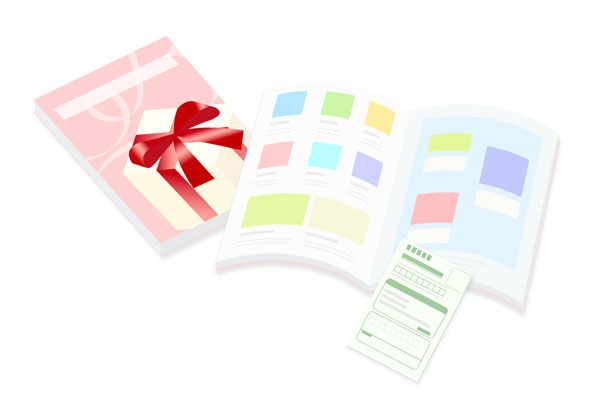
ここからは、カタログギフトを選ぶときのポイントを紹介します。
相手に喜んでもらえるものを選ぶために「贈る数を決める」「ジャンルを決める」「掲載商品が多いものを選ぶ」「予算を決める」という4つのポイントに絞ってお伝えします。
必要な数を決めないまま注文してしまうと不足がでたり、多過ぎてしまったりして再注文や返品手続きなどの手間や時間がかかってしまいます。
結婚式の引き出物や香典返しなど用意する数が多くなる場合は、リストなどを作成して、わかりやすく整理しておきましょう。
カタログギフトには、様々なジャンルが掲載されている総合的なカタログギフトと一つのジャンルに特化したカタログギフトがあります。贈る相手の年代がバラバラであったり、好みがわからなかったりする場合は、たくさんのジャンルが揃っている総合的なカタログギフトがおすすめです。
一方、相手のライフスタイルや趣味などが分かっている場合は、ジャンルを絞ったカタログギフトをおすすめします。例えば、インテリアにこだわりがある人には、おしゃれなショップのインテリア雑貨のカタログギフト、食べることが好きな人には、珍しい食品や高級感のある料理のカタログギフトなどがあります。
また、贈るシーンに特化したカタログギフトも用意されているので、どれを選ぶか迷った時には専用のカタログギフトを選べば間違いないでしょう。
掲載商品が多いカタログギフトは、日用品やグルメ、家電や旅行まで幅広く揃っているため、受け取った人が好みに合ったものを選びやすいです。
例えば、結婚内祝いの場合、いただいたお祝いの半額くらいの品物を贈るのがマナーです。また、シーンごとの相場は贈る相手との関係性によっても変わりますので、贈る相手やシーンごとの相場を確認してカタログギフトの予算を決めましょう。

例えば、受け取った人の声として以下のような内容があります。
「カタログギフトから品物を選ぶのが難しく期限を切らしてしまった」
「欲しいと思う商品がなかった」
「カタログギフトのシステムがよくわからない」
また、カタログギフトでは「贈り物として味気ない」「気持ちがこもっていない」と感じられる人もいます。
このようなカタログギフトを贈るデメリットを少しでも解消するために、カタログギフトを贈るときの注意点を解説していきます。
短い有効期限だと、忙しくしている間に期限が切れてしまい、カタログギフトを無駄にしてしまうことがあります。受け取った人が申し訳なく感じてしまい、気持ちを込めた贈り物が相手の負担になってしまいます。
もし有効期限を過ぎてしまったら一度カタログギフトを取り扱っている会社に連絡をしてみてください。基本的には期限が切れれば無効ではありますが、期限切れでも注文ができたり、代替え品を贈ってくれたりすることもあります。
期限が切れてしまった場合のフォロー体制の確認も大切です。
相手が好きなタイミングでゆっくりと選べるように配慮してカタログギフトを選びましょう。
インターネットからの申し込みであれば、普段使い慣れているスマホやパソコンからいつでも好きなタイミングで手続きが可能です。
ハガキの場合は、記入してポスト投函するという手間がかかります。しかし、インターネットに不慣れな人もいるので、ハガキでの申し込みに対応していることも必要です。
カタログギフトを受け取った人が申し込みの際に困らないように、申し込み方法を確認しておきましょう。
②カタログギフトは店舗とネットで購入できるが、それぞれにメリット・デメリットがあるため、贈るシーンや相手によってベストな購入場所を選ぶ
③カタログギフトは、香典返し、結婚祝い、出産祝い、新築祝い、各内祝いなどに使われる
④カタログギフトを選ぶ時は、相手が選びやすいように商品数が多いものや好みのジャンルを選び、贈る数を確認して予算に合わせて選ぶ
⑤カタログギフトを受け取った人が商品の注文をしやすいように、有効期限や注文方法に配慮する。また、アフターフォローについても確認しておく
カタログギフトが買える場所は店舗やネットショップなど様々です。この記事では、購入場所ごとのメリット、デメリットをそれぞれお伝えしていきます。
また、カタログギフトの選び方、活用できるシーンやカタログギフトを贈る際の注意点まで解説しますので参考にしてください。
目次
カタログギフトを買える場所は様々
カタログギフトが買える場所は、店舗であれば、百貨店や大型ショッピングセンター、ギフト専門店などで取り扱われています。また、ネットショップでもカタログギフトの購入が可能です。ネットショップには、百貨店やギフト専門店のショップもあり、店舗にはないカタログギフトをチェックできます。ネットショップのみで販売しているお店ではショップ独自のカタログギフトが用意されています。
様々な購入場所がありますが、カタログギフトを購入するタイミングや贈る相手によって買う場所を検討してみてください。
カタログギフトが買える場所

インターネットでの購入が不安な方は参考にしてみてください。
百貨店
百貨店にはギフトサロンが設けられており、個別の商品とともにカタログギフトも取り扱っています。目上の方や高齢の方へ贈る場合、有名百貨店のカタログギフトを贈ることで安心感があるでしょう。また、百貨店ごとにオリジナルのカタログギフトを展開していることもあるので、選択の幅が広がります。
大型ショッピングセンター
大型ショッピングセンターでもカタログギフトの購入が可能です。案内所やインフォメーションセンターなどで取り扱っています。普段の買い物でも活用している大型ショッピングセンターであれば、気軽に立ち寄れますし、買い物に行くタイミングでカタログギフトを買いに行けます。
大型ショッピングセンターは店舗展開も多く、違う店舗を比べることでカタログギフトの選択肢も増えるでしょう。
ギフト専門店
ギフト専門店は、お祝いの贈り物や内祝いに贈る品物を取り扱う専門店です。もちろん、カタログギフトも取り扱っています。カタログギフトを初めて購入する場合であれば特に、ギフト専門店ならではの知識を持ったスタッフに聞きながら選べるのでおすすめです。
ギフト専門店の店舗数はあまり多くないため、行ける範囲が限られるかもしれません。
カタログギフトを買う方法別のメリット・デメリット
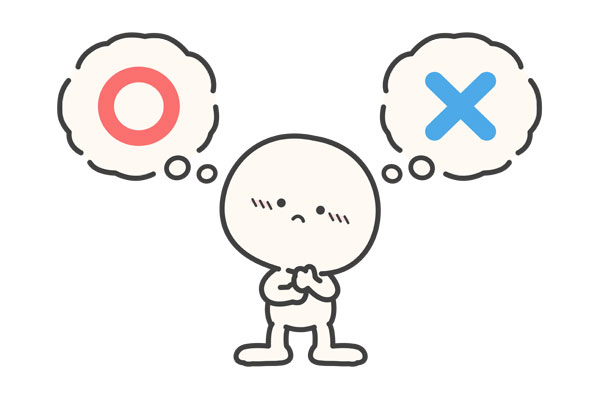
ここでは、カタログギフトを店舗で買う場合とネットで買う場合のそれぞれのメリット、デメリットを解説します。
店舗で買うメリット
店舗で買う一番のメリットは、実物のカタログギフトを手に持って確認できることです。実際に贈るカタログギフトの紙質や重さ、大きさ、高級感があるのかカジュアルな感じなのかなどを確認することで「持ち運びしやすく邪魔にはならないな」「意外と重いな」「もっと高級感が欲しいな」と気付くことができて、より相手に合ったカタログギフトを選べます。
また、カタログギフトを贈るシーンごとのマナーや、分からないこともその場で店舗スタッフに尋ねられるため、安心してスムーズにカタログギフトを選べます。
店舗で買うデメリット
店舗で買うデメリットは、お店まで出向く必要があることです。店舗が近くにあればいいのですが、遠方であれば、時間も交通費もかかってしまいす。店舗ではカタログギフトの現物が見られますが、取り扱っている全てのカタログギフトが展示されているとは限りません。そのため、店舗にあるカタログギフトの中から選ぶことになります。
また、店舗で買うと、配送伝票の記入が手書きであることがほとんどで、贈る数が多い場合は手間がかかります。手渡ししたい相手のためにカタログギフトを購入して、その場で持ち帰りができないこともあるので注意してください。
お中元やお歳暮の時期は、贈り物を買いにくる人が多いため、待ち時間が長くなることも考えられます。時間に余裕を持って店舗へ行くようにしましょう。
ネットで買うメリット
ネットで買うメリットは、自宅や好きな場所から自分のタイミングで購入できるところです。注文や配送伝票なども画面に入力するので、手書きに比べると手軽に手続きできるでしょう。ネットでは取り扱っているカタログギフト全てを確認できるので、様々な種類を比べて、より相手に合ったものを選べます。
多くのネットショップではデジタルカタログを使用して、画面上でカタログの中身が見られるようになっているため、自宅にいながらゆっくりと吟味できることもおすすめポイントです。
また、ネットで買う場合、送料無料やクーポンなどのお得なサービスが用意されているため、コストを抑えてリーズナブルにカタログギフトを購入できます。
さらに、カタログギフトの現物を贈るのではなく、オンライン上で贈れる商品もあるため気軽に贈ることも可能です。相手の住所がわからなくても贈れるショップもあります。
ネットで買うデメリット
ネットで買うデメリットは、カタログギフトの実物を確認できないことです。中のページは見られますが、重さや質感、分厚さなどはわかりにくいです。カタログギフトの実物を確認できないと不安な人は、ネットでの購入は避けたほうがいいでしょう。
また、疑問点を質問してもすぐに回答をもらえなかったり、スタッフの贈答マナーが不足していたりすることもあります。ネットショップのアフターフォローがどのようになっているかも確認が必要です。
まれに、贈り物にネットショップを利用することをよく思わない人もいるので、百貨店などのネットショップを利用するなど配慮しましょう。
カタログギフトはどんな時に贈る?

カタログギフトを活用できるシーンはいろいろありますが、ここでは、香典返し、結婚祝い、出産祝い、新築祝い、様々な内祝いでカタログギフトを贈る場合について解説します。
香典返し
香典返しは、いただいた香典の半分から3分の1を目安にお返しを考えます。相手に合わせたものを選ぶのが難しい場合も、カタログギフトであれば予算に合わせて選べますし、贈った相手に好きな品物を選んでもらえるので、おすすめです。
香典返しには細かなマナーや、しきたりが残っており、香典返しを贈る時期は、宗教や宗派によって変わります。仏式では四十九日の法要のあと1ヶ月の間に贈るのが基本とされています。
故人を思い、祈っていただいた方たちに失礼がないことが一番です。
結婚祝い
結婚祝いは、新しい門出を迎えた2人を祝福する贈り物です。カタログギフトであれば、新しい生活をスタートする2人が本当に望むものを選んでもらえます。また、2人で好きなものを選ぶ楽しい時間もプレゼントできるでしょう。
結婚祝いを渡すタイミングは、挙式がある場合は式の2ヶ月前から1週間前くらいの間が望ましく、挙式当日に渡すのはマナー違反とされています。
挙式がない場合は、結婚の報告を受けてから1ヶ月以内くらいに贈るようにしましょう。
出産祝い
出産祝いは、赤ちゃんの誕生のお祝いとともに、出産を終えたママへのプレゼントとしても贈られます。贈られた人が好きなものを選べるカタログギフトは、初めての出産の人でも兄弟姉妹がいる人へのお祝いでも、本当に必要なもの選んでもらえるおすすめの贈り物です。
出産祝いを贈るタイミングは、生後7日から1ヶ月くらいの間とされていましたが、近年、産後1週間ほど入院するように変わってきたので、産後2週間から3週間に贈るのがベストです。
新築祝い
新築祝いは、新しくお家を建てられたお祝いに贈ります。新築の家には建てた人の好みやこだわりが詰まっています。おしゃれなセレクトショップ監修のカタログギフトなど、新しいお家にあったインテリアや雑貨を選んでもらえる贈り物としておすすめです。
新築祝いに贈るにはタブーとされているものがあります。それは、「火事を思わせるもの」壁掛け時計のように「壁に穴を開ける必要があるもの」です。
カタログギフトは相手に好みのものを選んでもらうので、あまり心配はありませんが、赤い表紙のものは避けるのが無難です。
様々な内祝い
お祝いをいただいたらお返しとして贈るのが内祝いです。内祝いには様々なシーンがあり、結婚内祝い、出産内祝い、新築内祝いなどです。内祝いを贈る時には、贈るシーンごとにマナーがあり、地域によっても変わります。カタログギフトであればそれぞれのシーンに合わせて選べますし、贈るシーンに特化したカタログギフトも用意されています。
カタログギフトを選ぶときのポイント
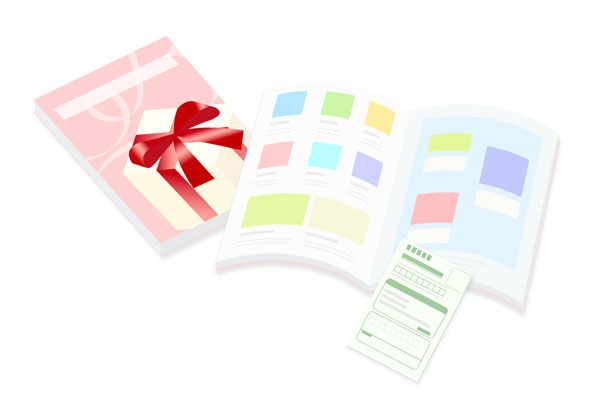
ここからは、カタログギフトを選ぶときのポイントを紹介します。
相手に喜んでもらえるものを選ぶために「贈る数を決める」「ジャンルを決める」「掲載商品が多いものを選ぶ」「予算を決める」という4つのポイントに絞ってお伝えします。
贈る数を決める
カタログギフトを選ぶ時にはまず、贈る数を確認することが大切です。必要な数を決めないまま注文してしまうと不足がでたり、多過ぎてしまったりして再注文や返品手続きなどの手間や時間がかかってしまいます。
結婚式の引き出物や香典返しなど用意する数が多くなる場合は、リストなどを作成して、わかりやすく整理しておきましょう。
カタログギフトのジャンルを決める
カタログギフトのジャンルはとても幅広く揃っています。グルメ、雑貨、日用品、旅行など様々です。カタログギフトには、様々なジャンルが掲載されている総合的なカタログギフトと一つのジャンルに特化したカタログギフトがあります。贈る相手の年代がバラバラであったり、好みがわからなかったりする場合は、たくさんのジャンルが揃っている総合的なカタログギフトがおすすめです。
一方、相手のライフスタイルや趣味などが分かっている場合は、ジャンルを絞ったカタログギフトをおすすめします。例えば、インテリアにこだわりがある人には、おしゃれなショップのインテリア雑貨のカタログギフト、食べることが好きな人には、珍しい食品や高級感のある料理のカタログギフトなどがあります。
また、贈るシーンに特化したカタログギフトも用意されているので、どれを選ぶか迷った時には専用のカタログギフトを選べば間違いないでしょう。
掲載商品が多いものを選ぶ
カタログギフトには掲載商品が数百点のものから1万点以上のものまであります。贈る相手の好みやライフスタイルがわからない場合や贈る相手の年代の幅が広い場合などは特に、掲載商品が多いものを選びましょう。掲載商品が多いカタログギフトは、日用品やグルメ、家電や旅行まで幅広く揃っているため、受け取った人が好みに合ったものを選びやすいです。
予算を決めて選ぶ
カタログギフトは数千円から数十万円もするものがあります。幅広い価格の中から選ぶには、カタログギフトを贈るシーンの相場に合わせることが大切です。例えば、結婚内祝いの場合、いただいたお祝いの半額くらいの品物を贈るのがマナーです。また、シーンごとの相場は贈る相手との関係性によっても変わりますので、贈る相手やシーンごとの相場を確認してカタログギフトの予算を決めましょう。
カタログギフトを贈るときの注意点

例えば、受け取った人の声として以下のような内容があります。
「カタログギフトから品物を選ぶのが難しく期限を切らしてしまった」
「欲しいと思う商品がなかった」
「カタログギフトのシステムがよくわからない」
また、カタログギフトでは「贈り物として味気ない」「気持ちがこもっていない」と感じられる人もいます。
このようなカタログギフトを贈るデメリットを少しでも解消するために、カタログギフトを贈るときの注意点を解説していきます。
有効期限を確認する
カタログギフトには有効期限があります。受け取った人がゆっくり好みのものを選べるように半年以上の有効期限があるカタログギフトを贈るのがおすすめです。短い有効期限だと、忙しくしている間に期限が切れてしまい、カタログギフトを無駄にしてしまうことがあります。受け取った人が申し訳なく感じてしまい、気持ちを込めた贈り物が相手の負担になってしまいます。
もし有効期限を過ぎてしまったら一度カタログギフトを取り扱っている会社に連絡をしてみてください。基本的には期限が切れれば無効ではありますが、期限切れでも注文ができたり、代替え品を贈ってくれたりすることもあります。
期限が切れてしまった場合のフォロー体制の確認も大切です。
相手が好きなタイミングでゆっくりと選べるように配慮してカタログギフトを選びましょう。
注文方法を確認する
カタログギフトの注文方法もあらかじめ確認しておきましょう。注文方法は、インターネットからの申し込みとハガキで申し込む方法があります。インターネットからの申し込みであれば、普段使い慣れているスマホやパソコンからいつでも好きなタイミングで手続きが可能です。
ハガキの場合は、記入してポスト投函するという手間がかかります。しかし、インターネットに不慣れな人もいるので、ハガキでの申し込みに対応していることも必要です。
カタログギフトを受け取った人が申し込みの際に困らないように、申し込み方法を確認しておきましょう。
まとめ
①カタログギフトは百貨店、大型ショッピングセンター、ギフト専門店の実店舗で購入可能。実店舗だけでなくネットショップも展開している②カタログギフトは店舗とネットで購入できるが、それぞれにメリット・デメリットがあるため、贈るシーンや相手によってベストな購入場所を選ぶ
③カタログギフトは、香典返し、結婚祝い、出産祝い、新築祝い、各内祝いなどに使われる
④カタログギフトを選ぶ時は、相手が選びやすいように商品数が多いものや好みのジャンルを選び、贈る数を確認して予算に合わせて選ぶ
⑤カタログギフトを受け取った人が商品の注文をしやすいように、有効期限や注文方法に配慮する。また、アフターフォローについても確認しておく
※本記事は公開時点の情報になります。 記事内容について現在の情報と異なる可能性がございます。
