香典返しのマナーと相場を解説!失敗しないカタログギフトの選び方も紹介
2025年9月1日
大切な家族を見送り、葬儀を終えた後に遺族が直面するのは、香典返しの準備です。個人への想いと共に寄せられた心遣いに感謝を込めてお贈りする香典返しは、品物選びや相場、マナーなど考えることが多く、精神的な負担になることも少なくありません。
近年では、相手の好みに合わせて選べるカタログギフトを香典返しの品として利用する方が増えています。
この記事では、香典返しにまつわる基本的なマナーや金額の目安、香典返しとしてカタログギフトを贈る際の失敗しない選び方などについて分かりやすく解説します。

まずは、香典返しの目的や金額の相場についてみていきましょう。
香典返しは、心遣いを形にする日本ならではの意味が込められており、故人の思い出を共有する手段として大切にされている慣習の1つです。
なお、葬儀や通夜の当日に渡される「会葬御礼」は、香典返しとは別のものです。会葬御礼は通夜や葬儀、告別式に参列してくださったすべての方への感謝と簡単なご挨拶として渡す手みやげで、500~1000円程度の消えものをお渡しするものであり、香典返しとは目的も相場も異なります。

例えば、一家を支えている働き手が亡くなり、子どもが未成年の場合などには、「香典は今後の生活に使ってください」という配慮が込められていることから、香典返しは3分の1、またはしなくてもよいとされています。
また、親族や身内から5万円~10万円といった多額の香典をいただいた場合には、「葬儀の足しにしてください」という意味が込められているため、半返しではなく、3分の1~4分の1程度の金額のお返しでよいとされているのです。
お住いの地域によっても相場が変わることがあるので、分からない場合には葬儀社の担当者や地域に住んでいるご高齢の方に聞いてみると良いでしょう。

しかし、香典返しとしてカタログギフトを贈ることは、贈る側にも受け取る側にもメリットがあり、今では多くの方に選ばれています。ここからは、その理由について見ていきましょう。
人の好みや興味はそれぞれなので、香典返しに限らずギフト全般を贈る際には必ずしも喜ばれるとは限りません。年齢や家族構成、生活スタイルが異なる多くの方に万人受けする商品選びは非常に難しく、それぞれに合うものを選ぶことは遺族にとって大きな負担になるでしょう。
その点、カタログギフトであれば、受け取る側がそれぞれ好きな品物を選べるので、好みに合わないものや不要なものを贈ってしまう心配がありません。
カタログギフトは、3万円以上の高額な香典返しにも対応できます。
高価な返礼品は「失礼にならないもの」「相手の好みに合っているもの」「生活スタイルに配慮したもの」を選ばなければと、特に気を遣うことになりがちです。
しかし、金額に応じたカタログギフトを贈ることで、気持ちがこもりつつも押し付けにならず、相手に喜んでいただける返礼が叶います。
遺族には葬儀を終えた後も、遺品の整理や相続手続きなど多くのやるべきことがあり、そんな中で参列者一人ひとりの香典額や好みに合わせた返礼品を個別に選ぶことは、時間的にも精神的にも大きな負担になりがちです。
カタログギフトであれば、金額に応じたカタログが用意されており、内容もパッケージ化されているため、マナーを保ちつつ効率的に準備できます。
香典返し専用のカタログギフトを取り扱うメーカーや百貨店の多くが、包装・のし、挨拶状の同封までを一括で対応してくれるサービスを提供しており、マナー面でも安心です。
こうしたセット対応で、遺族の準備の手間は大きく軽減され、受け取る方にもしっかりと丁寧な印象を与えられる点はカタログギフトの大きなメリットだといえるでしょう。
包装やのしも香典返し専用のデザインで用意されているものが多く、形式を守りつつも柔軟な対応ができます。遠方の親戚や取引先など、さまざまな立場の方へ送る際にも失礼になりにくい選択肢です。
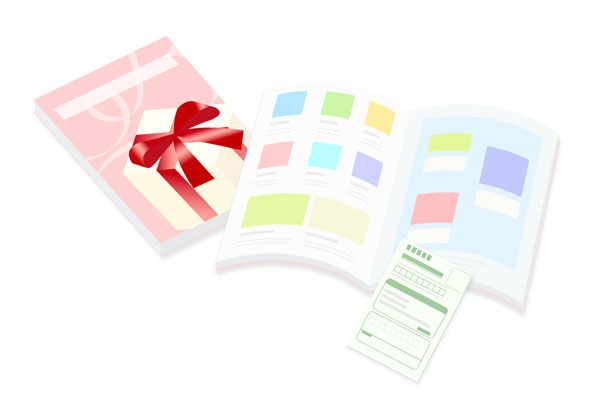
ここでは、香典返しとしてカタログギフトを選ぶ際のポイントと注意すべき点について具体的に解説していきます。
特に香典返しでは、「消えもの」と呼ばれる実用品や食品が好まれる傾向にあります。使えば無くなるもの、食べればなくなるものが充実しているかどうかもチェックポイントのひとつです。
また、香典返しカタログを選ぶ際には、注文方法にも配慮しましょう。高齢の方には、ページをめくって商品を選べる紙カタログのほうが、楽しく安心して利用できます。一方、若い世代にとってはスマートフォンやパソコンを使ったWeb注文対応が便利なため、オンライン注文に対応しているカタログの需要が高まっています。
注文スタイルの違いにも配慮することで、世代を問わず満足度の高い香典返しになるでしょう。
カタログの内容が同じでも、表紙のデザインだけを弔事用に変えられるものや、弔事専用のカタログギフトが販売されているので、そういったものを選ぶと失敗なく、マナー的にも安心して送れます。
また、挨拶状についても、故人の名前や喪主の名前を入れられること、忌明けの報告や感謝の気持ちを伝える文面をカスタマイズできるサービスがあると理想的です。
近隣に住む方や職場の方には、直接お礼の言葉と共に手渡しが望ましいとされています。送り方を選べるサービスを利用することで、効率的でありながらも失礼のない対応が可能です。
追加で購入できない場合、のしや挨拶状を新たに設定しなければなりません。1冊単位から注文できるか、配送やのし・挨拶状のセット対応が追加分にも適用されるかなどをチェックしておくと、いざというときに慌てずに済むでしょう。

注文するお店などによって、カタログの種類やその他のサービスに違いがあるため、それぞれの特徴について紹介していきます。
また、配送方法の選択肢も広く、個別配送や自宅への一括配送、追加注文の柔軟な対応など、忙しい遺族の負担を減らしてくれるサービスが充実しています。
こうした利便性と実用性の高さが、香典返しとしてのカタログギフトの人気のひとつだといえるでしょう。
また、店頭でスタッフに相談しながら決められるため、香典の金額や贈る相手に応じたカタログ選びに迷った際にも、プロのアドバイスを受けながら準備を進められる点も大きなポイントだといえるでしょう。
さらに、ポイント還元やタイムセールを活用することで、予算を抑えて注文できます。ショップによっては、香典返しに適した包装やのし、挨拶状の同封オプションが用意されています。
スマートフォンやパソコンから気軽に注文できる点や、日常的に使っているサイトから注文できる点は利便性の面で大きなメリットになるでしょう。
ただし、葬儀社が手配してくれるカタログギフトは、提携しているメーカーのものを勧めるケースが多いため、取り扱いのカタログギフトの種類や価格帯の選択肢が少ないことがあります。
こだわりのある品を選びたい場合や、贈る相手に応じて細かく選びたい場合は、事前に商品の内容や対応の柔軟性について確認してください。

最後に、実際の香典返しを選ぶ方から寄せられた疑問について、回答していきます。
しかし、地域によっては香典返しは一律に行う、香典の額に応じて少額でも返すといった慣習があるため、分からない場合には葬儀社の担当者や地域の高齢の方に確認してみるとよいでしょう。
会社の同僚など人数が多い場合には、お礼状を添えて簡単な品を配ることもあります。
ただし、相手から「香典返しはいりません」と辞退された場合には、ありがたくお気持ちを受け取り、返礼品を贈る必要はありません。
辞退されたにもかかわらず香典返しをお贈りする行為は、「葬儀などの足しにしてください」「遺族の今後の生活に役立ててください」という心遣いを無下にしてしまうことになり、逆に失礼に当たります。
香典返しを贈らない場合でも、他の方に香典返しを贈るタイミングでお礼状をお送りし、心遣いに感謝の気持ちを伝えるのが一般的です。
しかし、成人して自立した生活を送っている子や孫が香典を包んでくれた場合には、たとえ親子であっても香典返しを贈るのが一般的です。
②香典返しにカタログギフトが人気なのは、自由度の高さや金額に合わせて手配が可能な点、のしや挨拶状も一緒に頼めて効率的できちんとした印象を与えられるなど、多くのメリットがあるから
③香典返しにカタログギフトを選ぶ際には、弔事用としてふさわしいデザインかどうか、内容が年齢や性別を問わず喜ばれるものか、のし・挨拶状の対応があるかなどを確認する
④カタログギフトは、ギフト専門のネットショップや百貨店、オンライン通販サイト、葬儀社などで注文できるものの、それぞれメリット・デメリットを知った上で利用するのが望ましい
⑤香典が小額の場合は会葬御礼のみで済ませることもあるものの、喪主と同居している家族以外にいただいた場合には基本的に香典返しをするのが基本
近年では、相手の好みに合わせて選べるカタログギフトを香典返しの品として利用する方が増えています。
この記事では、香典返しにまつわる基本的なマナーや金額の目安、香典返しとしてカタログギフトを贈る際の失敗しない選び方などについて分かりやすく解説します。
香典返しとは?

まずは、香典返しの目的や金額の相場についてみていきましょう。
香典返しの目的
香典返しには、故人を偲び、香典をくださった方へのお礼といった意味合いを超えたいくつかの役割があります。四十九日法要を無事に終えたことを知らせる役割、遺族が悲しみを乗り越えて日常に戻るための節目、そして受け取る側が香典返しを通じて個人を偲びつつも気持ちを整える目的で贈られます。香典返しは、心遣いを形にする日本ならではの意味が込められており、故人の思い出を共有する手段として大切にされている慣習の1つです。
なお、葬儀や通夜の当日に渡される「会葬御礼」は、香典返しとは別のものです。会葬御礼は通夜や葬儀、告別式に参列してくださったすべての方への感謝と簡単なご挨拶として渡す手みやげで、500~1000円程度の消えものをお渡しするものであり、香典返しとは目的も相場も異なります。
香典返しの相場

例えば、一家を支えている働き手が亡くなり、子どもが未成年の場合などには、「香典は今後の生活に使ってください」という配慮が込められていることから、香典返しは3分の1、またはしなくてもよいとされています。
また、親族や身内から5万円~10万円といった多額の香典をいただいた場合には、「葬儀の足しにしてください」という意味が込められているため、半返しではなく、3分の1~4分の1程度の金額のお返しでよいとされているのです。
お住いの地域によっても相場が変わることがあるので、分からない場合には葬儀社の担当者や地域に住んでいるご高齢の方に聞いてみると良いでしょう。
香典返しにカタログギフトが選ばれる理由

しかし、香典返しとしてカタログギフトを贈ることは、贈る側にも受け取る側にもメリットがあり、今では多くの方に選ばれています。ここからは、その理由について見ていきましょう。
受け取る側の自由度が高い
香典返しとしてカタログギフトを選ぶ最大のメリットは、受け取る側が自分の好きなものを選べる自由度の高さです。人の好みや興味はそれぞれなので、香典返しに限らずギフト全般を贈る際には必ずしも喜ばれるとは限りません。年齢や家族構成、生活スタイルが異なる多くの方に万人受けする商品選びは非常に難しく、それぞれに合うものを選ぶことは遺族にとって大きな負担になるでしょう。
その点、カタログギフトであれば、受け取る側がそれぞれ好きな品物を選べるので、好みに合わないものや不要なものを贈ってしまう心配がありません。
金額に応じたカタログを選べる
カタログギフトは複数の価格帯のものが用意されているため、半返しの相場に合ったものを選びやすく、1ブランド内で複数の価格帯のカタログを一度に注文可能です。カタログギフトは、3万円以上の高額な香典返しにも対応できます。
高価な返礼品は「失礼にならないもの」「相手の好みに合っているもの」「生活スタイルに配慮したもの」を選ばなければと、特に気を遣うことになりがちです。
しかし、金額に応じたカタログギフトを贈ることで、気持ちがこもりつつも押し付けにならず、相手に喜んでいただける返礼が叶います。
忙しい遺族の負担軽減
香典返しにカタログギフトを選ぶと、遺族の負担は大きく軽減されます。遺族には葬儀を終えた後も、遺品の整理や相続手続きなど多くのやるべきことがあり、そんな中で参列者一人ひとりの香典額や好みに合わせた返礼品を個別に選ぶことは、時間的にも精神的にも大きな負担になりがちです。
カタログギフトであれば、金額に応じたカタログが用意されており、内容もパッケージ化されているため、マナーを保ちつつ効率的に準備できます。
のし・挨拶状の対応が簡単
香典返しにカタログギフトが選ばれる理由のひとつに、のしや挨拶状の対応が簡単な点が挙げられます。香典返し専用のカタログギフトを取り扱うメーカーや百貨店の多くが、包装・のし、挨拶状の同封までを一括で対応してくれるサービスを提供しており、マナー面でも安心です。
こうしたセット対応で、遺族の準備の手間は大きく軽減され、受け取る方にもしっかりと丁寧な印象を与えられる点はカタログギフトの大きなメリットだといえるでしょう。
地域や宗派を問わず使いやすい
香典返しは、地域ごとに異なる風習や慣習があり、品物の種類や包装、表書きの表現など、細かな違いに配慮が必要な場合があります。その点、カタログギフトは全国的に受け入れられやすく、地域の慣習に左右されにくい汎用性の高い返礼品として重宝されているのです。包装やのしも香典返し専用のデザインで用意されているものが多く、形式を守りつつも柔軟な対応ができます。遠方の親戚や取引先など、さまざまな立場の方へ送る際にも失礼になりにくい選択肢です。
カタログギフトの選び方
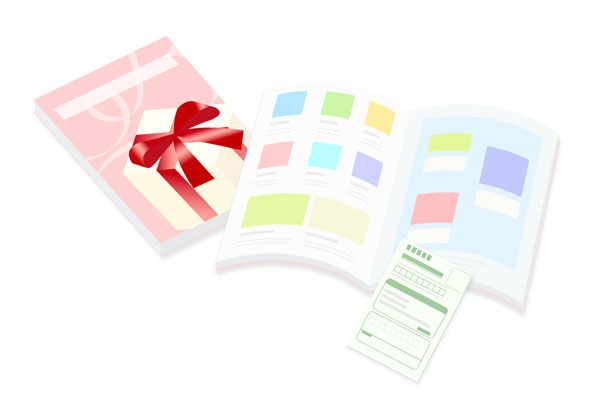
ここでは、香典返しとしてカタログギフトを選ぶ際のポイントと注意すべき点について具体的に解説していきます。
カタログギフトの内容を確認
香典返しとしてカタログギフトを選ぶ際には、まずは内容の充実度を確認することが大切です。年齢や性別、家族構成、ライフスタイルを問わず幅広く喜ばれる内容であるかが満足度に大きく影響します。食品や雑貨、体験型ギフトなど、選択肢が豊富なカタログを選ぶと、受け取った方の好みに柔軟に対応が可能です。特に香典返しでは、「消えもの」と呼ばれる実用品や食品が好まれる傾向にあります。使えば無くなるもの、食べればなくなるものが充実しているかどうかもチェックポイントのひとつです。
また、香典返しカタログを選ぶ際には、注文方法にも配慮しましょう。高齢の方には、ページをめくって商品を選べる紙カタログのほうが、楽しく安心して利用できます。一方、若い世代にとってはスマートフォンやパソコンを使ったWeb注文対応が便利なため、オンライン注文に対応しているカタログの需要が高まっています。
注文スタイルの違いにも配慮することで、世代を問わず満足度の高い香典返しになるでしょう。
弔事用のデザインかどうか
香典返しとしてカタログギフトを選ぶ際には、弔事の雰囲気に合ったデザインのものを選ぶこともポイントのひとつです。表紙が黒やグレー、紺色などの落ち着いた上品なデザインであること、洋風よりも和風のデザインでカジュアル過ぎないものがおすすめです。カタログの内容が同じでも、表紙のデザインだけを弔事用に変えられるものや、弔事専用のカタログギフトが販売されているので、そういったものを選ぶと失敗なく、マナー的にも安心して送れます。
のし・挨拶状の対応があるか
香典返しにカタログギフトを選ぶ際には、のしや挨拶状の対応があるかもチェックすべきポイントです。仏教では「志」や「満中陰志」、神道では「偲び草」、キリスト教では「感謝」といったように、地域や宗教によって表書きが異なるため、ご自身の宗派に合ったものを選べることも確認しましょう。また、挨拶状についても、故人の名前や喪主の名前を入れられること、忌明けの報告や感謝の気持ちを伝える文面をカスタマイズできるサービスがあると理想的です。
送付方法の柔軟性
香典返しのカタログギフトを選ぶ際には、送付方法の柔軟性があるかどうかもポイントです。遠方に住む方や住所が分かっている方には個別に配送してもらい、手渡ししたい分は自宅などにまとめて送ってもらえると、時間的な負担が大幅に軽減できます。近隣に住む方や職場の方には、直接お礼の言葉と共に手渡しが望ましいとされています。送り方を選べるサービスを利用することで、効率的でありながらも失礼のない対応が可能です。
追加購入ができるかどうか
香典返しの準備では、後になって香典をいただいたり、うっかり手配漏れが発覚したりすることも珍しくありません。そのため、追加でカタログギフトを購入できるかどうかも事前に確認しておきたいポイントです。追加で購入できない場合、のしや挨拶状を新たに設定しなければなりません。1冊単位から注文できるか、配送やのし・挨拶状のセット対応が追加分にも適用されるかなどをチェックしておくと、いざというときに慌てずに済むでしょう。
カタログギフトの種類

注文するお店などによって、カタログの種類やその他のサービスに違いがあるため、それぞれの特徴について紹介していきます。
ギフト専門のネットショップ
ギフト専門のネットショップでは、冠婚葬祭向けの専用カタログが豊富に取り揃えられています。価格帯や商品カテゴリーの選択肢が細かく設定されており、包装・のし・挨拶状などの対応もオンライン上で指定できるので、短期間で準備したいときに便利です。また、配送方法の選択肢も広く、個別配送や自宅への一括配送、追加注文の柔軟な対応など、忙しい遺族の負担を減らしてくれるサービスが充実しています。
こうした利便性と実用性の高さが、香典返しとしてのカタログギフトの人気のひとつだといえるでしょう。
百貨店
百貨店のカタログギフトは、品質や信頼性が高く、目上の方にも安心して贈れるラインナップで多くの方に選ばれています。香典返しとして贈る際にも、弔事にふさわしい落ち着いた上品な包装や、宗教・地域に合わせた表書きへの対応もあり、挨拶状の文面のカスタマイズについても細かく配慮されているのが特徴です。また、店頭でスタッフに相談しながら決められるため、香典の金額や贈る相手に応じたカタログ選びに迷った際にも、プロのアドバイスを受けながら準備を進められる点も大きなポイントだといえるでしょう。
オンライン通販サイト
楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングなどの大手オンライン通販サイトでも、香典返し用のカタログギフトを手軽に選べます。これらのサイトのカタログギフトの特徴は、幅広い価格帯やジャンルの商品が揃っていることに加え、購入者のレビューを参考にしながら選べる点です。さらに、ポイント還元やタイムセールを活用することで、予算を抑えて注文できます。ショップによっては、香典返しに適した包装やのし、挨拶状の同封オプションが用意されています。
スマートフォンやパソコンから気軽に注文できる点や、日常的に使っているサイトから注文できる点は利便性の面で大きなメリットになるでしょう。
葬儀社
利用する葬儀社によっては、香典返し用のカタログギフトを手配まで一括してサポートしてくれるサービスを提供しています。のしや挨拶状も含めて一括で準備を任せられるため、遺族の負担が大幅に軽減される点が大きなメリットです。ただし、葬儀社が手配してくれるカタログギフトは、提携しているメーカーのものを勧めるケースが多いため、取り扱いのカタログギフトの種類や価格帯の選択肢が少ないことがあります。
こだわりのある品を選びたい場合や、贈る相手に応じて細かく選びたい場合は、事前に商品の内容や対応の柔軟性について確認してください。
香典返しでよくあるQ&A

最後に、実際の香典返しを選ぶ方から寄せられた疑問について、回答していきます。
香典の額が少額だった場合にも香典返しは必要ですか?
香典は、一般的には半返しが基本とされています。ただし、香典の金額が3000円以下の場合は返礼品の方が高くついてしまうこともあるため、会葬御礼のみで済ませ、香典返しは無しにすることが多いようです。しかし、地域によっては香典返しは一律に行う、香典の額に応じて少額でも返すといった慣習があるため、分からない場合には葬儀社の担当者や地域の高齢の方に確認してみるとよいでしょう。
連名でいただいた場合の香典返しはどうしたら良いですか?
香典を連名でいただいた場合には、代表者に香典返しをひとつ渡すのが基本的なマナーです。ただし、一人当たりの金額が5000円を超える場合には、個別に香典返しを用意することも検討してみてください。会社の同僚など人数が多い場合には、お礼状を添えて簡単な品を配ることもあります。
親族にも香典返しをするべきですか?
どんなに近しい親族であっても、基本的には香典返しをするのがマナーです。香典返しは、香典をいただいたことへの感謝に加え、忌明けである四十九日を無事に迎えたことを報告する意味合いがあることがその理由です。ただし、相手から「香典返しはいりません」と辞退された場合には、ありがたくお気持ちを受け取り、返礼品を贈る必要はありません。
辞退されたにもかかわらず香典返しをお贈りする行為は、「葬儀などの足しにしてください」「遺族の今後の生活に役立ててください」という心遣いを無下にしてしまうことになり、逆に失礼に当たります。
香典返しを贈らない場合でも、他の方に香典返しを贈るタイミングでお礼状をお送りし、心遣いに感謝の気持ちを伝えるのが一般的です。
喪主でない場合、香典返しは必要ですか?
喪主の配偶者や喪主と一緒に暮らしている子どもや孫は、香典を出さないため、香典返しも不要です。しかし、成人して自立した生活を送っている子や孫が香典を包んでくれた場合には、たとえ親子であっても香典返しを贈るのが一般的です。
まとめ
①香典返しは、葬儀の際に香典をいただいた方へ、感謝の気持ちとして贈る品物のことで、通常は忌明けの四十九日を過ぎた後に半返し(いただいた金額の半分のお礼)で贈るのが一般的②香典返しにカタログギフトが人気なのは、自由度の高さや金額に合わせて手配が可能な点、のしや挨拶状も一緒に頼めて効率的できちんとした印象を与えられるなど、多くのメリットがあるから
③香典返しにカタログギフトを選ぶ際には、弔事用としてふさわしいデザインかどうか、内容が年齢や性別を問わず喜ばれるものか、のし・挨拶状の対応があるかなどを確認する
④カタログギフトは、ギフト専門のネットショップや百貨店、オンライン通販サイト、葬儀社などで注文できるものの、それぞれメリット・デメリットを知った上で利用するのが望ましい
⑤香典が小額の場合は会葬御礼のみで済ませることもあるものの、喪主と同居している家族以外にいただいた場合には基本的に香典返しをするのが基本
※本記事は公開時点の情報になります。 記事内容について現在の情報と異なる可能性がございます。
